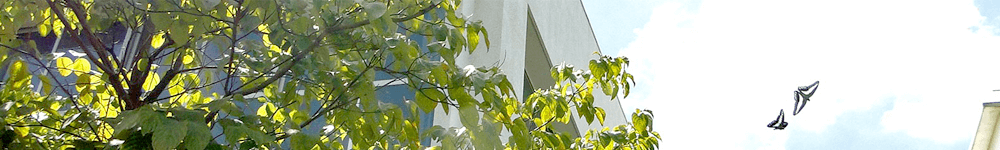こぼれ話
こぼれ話New
その553 有隣岩探索始末 2025.12.3
2025/12/03
こぼれ話その547「拾い物」で、
明治初期に長州から逃れて土佐に潜伏した富永有隣のことを書いた。
大豊町で名主や庄屋の家に世話になって転々とし、
追手が迫った時に隠れた有隣岩があることを知って、ぜひ行ってみたいと思った。
昭和46年頃の大豊町役場が発行した広報誌に、
郷土史家の橋詰延寿さんが富永有隣のことを詳しく執筆していらっしゃる。
先祖が有隣をかくまったという地元の方が橋詰さんを案内し、
有隣岩の入口の写真も載っている。
概略は「案内の方の家から山道を歩いて三十分、
ここを上がれば峠へ出る所を左へ曲がると有隣岩」という記述であった。
この3月以降、何度も山に入った。
橋詰さんの記述から出発点はわかっているのだが、
山への道が薄い踏み跡しかない。
踏み跡を進むと幅の広いしっかりした山道に出た。
この道は北西に進んでいて、方角的にはいい感じだ。
そんな探索を繰り返し、2つの三角点にも至ったが、
三角点の付近では隠れ家とするには遠すぎる。
枝道にも入ってみたが、途中で道が細くなって消える。
9月頃には有隣岩を探すのはあきらめようか、と思っていた。
10月に入り、橋詰さんが出発した地点から北西を探すのではなく、
反対の西側から東を探ることにした。
南西側から先に述べた三角点の一つに到る道がある。
その枝道を探った。
一つ目の分岐は南に下りすぎて道がなくなる。
二つ目の分岐は道が細くて消えそう。
三つ目の分岐は三角点への分岐でありここを反対の東へ入った。
しかしこの道もやがて消える。
ここで地図アプリが大変に役立った。
以前に東側から歩いた山道で、途中で引き返した場所があった。
その引き返した地点が、現在地のすぐ南にある。
斜面をズリズリと下り、かつて来た山道に降り立って、まだ歩いたことのない西方向に進む。
少し道が細くなって傾斜がきつくなったあたりで山肌に岩のくぼみがあった。
あまり奥行はなさそうで一度は通り過ぎたが、
まあ写真を撮っておこうと考えて元に戻った。
くぼみの奥をのぞくと向こうが光っている。
穴は向こうに抜けて、太陽の光がこちらに来ているのだ。
橋詰さんの記述から、有隣岩の穴が向こうに抜けていることは知っていた。
多分、有隣岩だろう。
穴は最初少し狭い所があって、しゃがんで進むのだがすぐに広くなる。
カマドウマが何匹か跳ねた。壁からぶら下がっているコウモリもいる。
途中から人工的に掘ったような丸い天井になって、すこし背を屈める程度で歩ける。
向こうへ抜けると、入口より広い出口だ。
出口が広いことも橋詰さんの記述に合致する。
恐らく有隣岩に間違いないと思うのだが、
橋詰さんの記述と合わない点もいくつかある。
最も大きく合わないのは、橋詰さんの記述にある
「最初の穴の下へまた穴の入口ができている。
~かなり広い所があり~人数も五、六人―いや十人ほどは平気で入れる。」というところ。
私の見つけた穴の下は少し急な斜面で、
慣れないロープを使って降りてみたが、入口の下に別の穴はない。
もしかして出口の下かも、と思ってその下も探したがやはり別の穴はない。
橋詰さんの頃から50年以上経過しているので、下の穴は潰れてしまったのか。
それとも私の見つけた穴は有隣岩ではなかったのか。疑問が残る。
今回の探索に大豊町の方は大変に親切でした。
平成の初め頃に橋詰さんとは別の作家の方を案内した
郵便局長さんがおいでることが分かった。
その郵便局を訪ねてみると、
今の職員さんは約35年前の郵便局長さんのことはご存じなかったが、
「この人と話してみて。」と近隣の方に電話して下さった。
そこから定福寺の方とつながり、
さらに有隣が捕縛されたお家の方にもお目にかかることができた。
また、地域の集会所で初対面の私が
「富永有隣の岩を探しているのですが。」というと、
「さあ、知らんねえ。母からも聞いたことがない。
けんど知っちゅう人がおるかもしれん。聞いてみるき。」
と言われて折り返しのお電話をいただいたことがあった。
お電話をいただいた方は、小学生の頃に岩に行ったことを覚えていると言われる。
実際にお会いし多くの地図や資料をいただいき、
ここから入れば行けるのでは、というアドバイスもいただいた。
この方に、私が発見した岩穴のことをご報告すると、
「おめでとうございます。子供の頃の記憶と一致します。」とご返事をいただいた。
人には思い切って声をかけて聞いてみること、
これが有隣岩探索で私の一番の得たものでした。
大豊町の皆様、大変ありがとうございました。